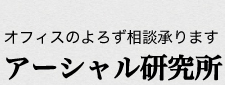“稼ぐオフィス”は、
何のために変革するのかを知っている、
“稼がないオフィス”は、
何だかわからないので他社に任せる
皆様こんにちは!
稼ぐオフィス構築コンサルタントの寺崎です。
今回は、<「デザイン思考」のとり入れ方>をお話したいと思います。
ハーバード・ビジネス・レビュー紙6月号では、「デザイン思考」を社会技術として説明していました。この社会技術とは、「手法と考察が一体となって業務プロセスに反映されること」と定義されています。
このことによって、著しい改善がなされることです。分かりやすい例として、1980年代の日本の製造業での「TQM(トータル・クオリティ・マネジメント)」が紹介されていました。中でもトヨタの、かんばん方式、QC活動によって、また現場力という気づきから、著しい改善ができたことが挙げられます。
デザイン思考という言葉が出回り始めたのは、そんなに昔のことではありません。実際オフィスに取り入れられるようになったのは2000年代に入ってからです。現在の提唱者は、IDEO社長兼CEOのティム・ブラウン氏がいます。彼の著した本を読んでもわかることですが、デザイン思考だから、「きれいなオフィス」をつくるということではないということです。
言い方を変えれば、使う人の喜ぶ姿、補う仕様を思いやってデザインすることなのです。ですから、ある時はシャープなデザインで切りやすい工具をつくることもありますし、別の時には、無骨なデザインをすることもありえます。カッコ悪くても使い心地を優先して、使う人に喜びを与えられれば良いのです。
デザイン思考は仕組みではなく方法です。人によって理解の仕方も異なり、使い方、とり入れ方ひとつで、”稼ぐオフィス”にも”稼がないオフィス”にもなり得ます。
”稼がないオフィス”は、表面上のデザインに執着して、見た目優先のオフィスをつくります。改装・移転を機に、オフィス関連業者のデザイナーに説得されて、「デザイン思考」のとり入れ方を間違ったオフィスをつくります。
社員が集まるコーナーをカフェのようにして、リビングのようにして、モチベーションを上げる仕組みのように錯覚させます。「優れたオフィスデザインで、○○オフィス大賞の条件をクリアーしてますよ。応募しましょうね」とすすめられて、受賞のために、単なる方法を取り入れただけのオフィスで満足します。
しかしそこに「モチベーションを上げる仕組み」はないのです。
その点、“稼ぐオフィス”の目的は、オフィスからも稼ぎ出す仕組みにすることです。何かのショーレースに参加することが目的ではありません。立派で手入れにもお金がかかるデザインは不要です。
受付壁をグリーンで覆って、滝のように水を流すような仕掛けよりも、来客と共創するのに効果を発揮する仕掛けづくりに「デザイン思考」をとり入れます。「創造の場」「提案の場」「商談の場」にする仕掛けに資金をつぎ込みます。すべては訪問客の新たな儲けを生み出す為の、“社員が思考するオフィス”の仕組みを導入します。
具体的には、部屋全体を執務エリア6:商談エリア4に分割します。執務を奥、商談を手前に配置します。
また、全体を3つの輪で囲んで、交わるエリアをコミュニケーションスペースに割り当てます。
3つの輪とは、「3つの場」のことです。
平面図上の入り口、手前に「商談の場」を設けて、右上と左上に「創造の場」「提案の場」を配置します。
コミュニケーションスペースは、ミーティング用に可動容易なテーブル、チェアで構成して、人数に対応します。執務エリアと商談エリアの境に壁を建てますが、あくまでも区分けするためです。
イメージとして、執務エリアは学校の教室。
商談エリアはコ・ワーキングスペースのような感じです。
全体の家具は可変性を考慮した仕様を選びます。学校では、スクール形式で先生の方向に皆が向く形もできますし、班にしてグループ活動や給食を食べたりします。その場にある家具を動かしてフル活用していませんでしたか?オフィスも同じように考えます。
要はみんなで「個人の考え」を発表するため、映し出したり、貼り出したりできるようにします。ワイガヤして、一つのものにまとめるという活動をしやすくすることで、ワークショップをしたり、試作品を作ったりできるようにします。コ・ワーキングスペースは、執務室とは違う家具を選び、セキュリティ面に配慮するだけです、あとは変わりません。
顧客と共創してイノベーションを生むためには、内装を重視するよりも、可変性を考慮して、アイデアを出し合い、意見を交換し、まとめる「創造の場」や、一人から数名で訪れる顧客のために「提案の場」へと変化させ、プロトタイプを何度も作り変えて顧客に働きかける「商談の場」へと誘うように、3つの機能を最大限活かす仕掛けを重視します。
観察力と直観力で「こういうのかな?」とプロトタイプをつくり「こんなものかな?」と準備して、最後にコラボレーションから顧客との関与・対話・学習を重ねることです。
デザイン思考の手法には他にも、エスノグラフィック調査、リフレーミング、実験の重視、多様性のあるチーム活用などがあります。しかし細かい理屈はいりません。
「デザイン思考」とは、自社の製品・サービスを利用してくださる顧客に「もっと便利でより良い方法を一緒に考え、やり方まで寄り添ってあげること」だと言えます。ですから「会社には、様々な視点や感情をもつ人間が集まっている」という理解で、一人ひとりの考えを出しやすく、伝える術を磨き、まとめる場の設計こそが、賢い社長のなさるべきことなのです。
「デザイン思考」をうまく取り入れることによって「手法と考察が一体となって業務プロセスに反映されること」になります。”稼ぐオフィス”へと著しい改善がなされるのです。
「とにかく考えろ」「売るためにできることに集中しろ」「コラボレーションでつくり出せ」と号令をかけることよりも、まず個人のアイデアをカタチにする場をつくって、社員達が顧客との関与・対話・学習できるように仕組むことが大切であると考えます。
最後にもう一つ、日本が1980年代に活躍できた秘訣として、仲間意識、結束力、チームワークという強力な武器があったことを忘れずにいて欲しいと思います。社長はこれらを発揮させる仕組みを導入すれば、ハッパをかける気苦労から解放されます。
あなたのオフィスに取り入れる「デザイン思考」とは顧客のための変革の仕組みですか?
それとも、ただの「デザインされたオフィス」と呼ばれる方法だけで満足しますか?